9月19日(月)
5日目の午前中はボストン・スクールの授業に参加させていただきました。
ボストン・ラテン・スクールは、アメリカでは最初の公立高校であり、現存する最古の学校です。その名の通り、本当に歴史ある素晴らしい学校で、3人の大統領を輩出したとのことで、大きなホールには著名な方の肖像画が多数飾ってありました。





ここで生徒たちは、ホームルームから、一人ずつ分かれてホスト役の生徒と一緒に実際の授業を見学しました。
この学校では、先生は移動せず、生徒が先生の教室に授業を受けに行くという仕組みです。
実際にアメリカトップレベルの授業に参加した生徒たちは、いろいろ学ぶことが多かったようです。
何より刺激になるのは、生徒たちがとても積極的に授業に参加していること。
チャイム(ブザー?)がなると、特に挨拶もなく一斉に次の授業に移動していく様子も新鮮でした。時間を無駄にしない時程は、なんとお昼休みが18分ということで、とてもびっくりしました。
お昼はランチをいただいて、次は近くにあるボストン美術館に行ってきました。
2時間という時間をとったのですが、その時間では到底回ることができず、その迫力に圧倒された時間でもありました。 




その後はいよいよ最終プレゼンの待つボストン公共図書館に移動。
この日のプログラムは総まとめともいう意味もあり、レクチャーあり、被爆者の方の話あり、会場も交えての質問コーナーも入れながらのデスカッション、そして生徒たちの感想、プレゼン、と盛りだくさんの内容でした。
ここでは昨日のグループワークの成果も発表しました。アメリカの高校生とともに考えてアイデアを発表するというこのスタイルは、とても刺激的で良い機会ではなかったでしょうか。




また、ボストン公共図書館は、パブリックということもあり、一般の方も聴きに来ることができたのですが、会場は満員、その関心の高さにびっくりしました。
生徒たちの最終プレゼンは、少し間違えても臨機応変に、堂々とプレゼンを行うことができました。
「東京オリンピックアーカイブ1964ー2020」にどう関わってきたか、その取り組みはどんなものか、そしてどんな意味があるのか、真摯に丁寧に伝えることができた時間だと思います。







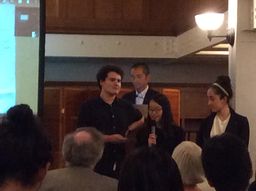

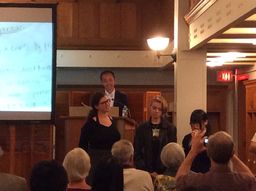



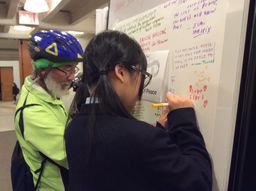
最後に一緒に時間を過ごした仲間たちや、スタッフの方々、支えてくれた大学の先生方などと歓談し、抱き合い、写真を取り合ったりしました。




その後は、渡邉先生や院生たちと素敵なお店で食事をしました。
長いようであっという間の時間、あすはいよいよ帰国です。
さて、今回の日米高校生平和会議に参加して、生徒たちはどんなことを学び、何を考えたのでしょうか。
この日米・高校生平和会議の様子はさまざまなメディアでも取り上げてくださっています。
TBS「報道特集」での放映の様子はこちらから